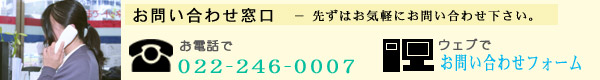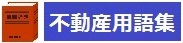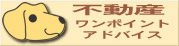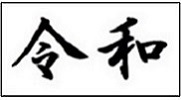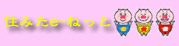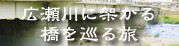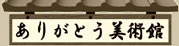2025年1月号 | レポート
<令和7年の干支は乙巳(きのとみ)>
新しい年を迎え、「あけましておめでとうございます 今年も宜しくお願い申し上げます」!! との挨拶が交わされたことでしょう。令和7年がスタートしました。
【写真左】行く年(於 蒲生)【写真右】新年(於 蔵王)
人々の幸せを願うとともに、それぞれ1人1人が目標を持ち、花を咲かせ、秋には実を結ぶ新しい年の始まりです。
今年は冬本番となる1月中旬~2月中旬の前倒しなのか、正月早々から大雪と厳しい寒さに見舞われております。
私たちの意思で変えることができませんので、肝要なのは「受容する」姿勢です。
厚着をしたり適切に暖房を使うことや、鍋物などの温かい食べ物が美味しい季節でもありましょう。
題名「春」 「少しずつ裸木の木から解ける雪」 雪雄
Ⅰ【 令和7年の干支は乙巳(きのとみ) 】
クネクネとしたヘビを気味悪がる人も多いですが、一方で“金運アップの象徴”としてのヘビが脱皮した抜け殻やヘビのチャームをサイフに入れたりヘビを形どった指輪などのアクセサリーを身に付ける人もいます。
ヘビが金運と結びついているのは、インドでは白蛇が金運をつかさどる弁財天の化身とされていること、また「巳」と「実」が同じ「み」の発音で、実(巳)入りする=収入がある とする掛け言葉ともなっている。
金運を願う人は、「12日に一度巡ってくる『巳の日』を選んで神社にお参りする」といいらしい。
さらに、60日に一度の「己巳(つちのとみ)」の日で各地の弁天様は多くの参拝客でにぎわう。宝くじ売り場などには「本日巳の日」と貼り出して販売増を狙うところもあるという。
ちなみに、金運アップのみならず、前記のとおり大雪に見舞われることは、やはり巳(蛇)年の干支の特徴かも知れません。昨年の干支「甲辰(龍)」と蛇との習合として、湿地を好んで生息する習性に基づき、水神の使いとも信仰されて来ておるようです。
思うに、弁財天神の多くは、(池の中や側にある。)縁日(巳待講)は、巳の日に行われるのはそうした由来によるものでしょう。
水は「巳」や「龍」との関連性があり、さらに水は水田の稲作に欠かせない。大平山神社(栃木県)には蛇が田を守る神として祀られている社がある。
従って、今年は雨量が多くなり、実りの年となるかも知れません。
Ⅱ【 昨年に多賀城碑が1300年を迎え、万葉集編纂1300年 】
昨年2024年10月11日に、多賀城は国の特別史跡に指定されました。
多賀城に奈良時代より陸奥国府や鎮守府が置かれ、平安時代(11世紀中頃※1)まで東北地方の政治・軍事・文化の中心であった。
多賀城史跡の入口に立つ「多賀城碑※2」は、西暦724年(神亀元年)に大野東人によって創建されてから丁度1300年に当たった年でもありました。
続日本紀※3西暦737年(天平9年)に北方を固める目的で「多賀柵」を設置した。(故 伊東信雄氏出典)
他にも牡鹿柵・玉造柵・色麻柵等を充てたとする文献がある。
1300年前と言えば、日本に現存する最古の「万葉集」歌集の編纂に加わった大伴家持※4(おおとものやかもち)は生涯で最大の業績を残した。また、多賀城との縁もあった※5。
京から越中国(現在の富山県)に5年赴任し、歌数は223首を歌っている。その後、因幡国(現在の鳥取県)で759年正月1日の新年の宴の歌「新しき 年の始の初春の 今日降る雪のいや重吉事(雪のように次々重なれ良き事よ)」を最後に、万葉集は閉じられています。その後家持は重要な役職につき、鎮守府将軍の身分として「多賀城」に赴任した。(家持65歳となった。)
家持は、元々歌が生きる糧であった筈なのに、陸奥の国(現在の多賀城)で一首の歌も残されていないことから見て、何か特別な事情(健康的な面)があったのかも知れません(私見)。(没 68歳)
家持の歌はどこか寂しく、叙情的な歌が多い。
家持の身分は元々低い家柄の出ではありましたが、父親は大伴家の跡取りとして、貴族の子弟に必要な学問・教養を早くからしっかり学んでいましたが、父の旅人とは14歳の時に死別している。
思うに、家持が「万葉集」の編纂に当たっては、天皇から農民まで身分には関係なく歌を中心にした背景からも考察される。また、地域も東北から九州までも含まれている。家持が多賀城に赴任中の歌も資料が発見されるかも知れません。そして国宝となった多賀城跡を訪ねると思われる歌人や歴女などを中心に多くの観光客の来訪が期待されます。
「降り仰(さ)けて 若月見れば一目見し 人の眉引き思ほゆるかも」(家持)
(意味:空をふり仰ぎ三日月を見ると、一目見ただけのあの方の眉が想い出される。家持16歳時に詠んだ歌)
<注釈>
※1 11世紀とは、西暦1001年から1100年までの100年間(ただし、検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分である。出典の追加資料が求められている。)
※2 多賀城碑とは、多賀城市大字市川にある奈良時代の石碑。国宝に指定されている。一部は762年の改修を伝える。加えて書道史の上から、日本三古碑の1つとされる。歌枕の一つである「壺の碑」として知られている。
※3 続日本紀とは、平安時代初期に編纂された勅撰史書。
※4 大伴家持とは、「万葉集」を編纂した現存するわが国最古の歌集を残した。父親の大伴旅人と万葉歌人です。その様な歌人という環境で育ったことも影響したのかも知れません。歌集の特徴は、天皇から農民まで幅広い階層に及び詠み込まれた。地域は、東北から九州に至り全20巻からなる約4500首で構成されている。
以上